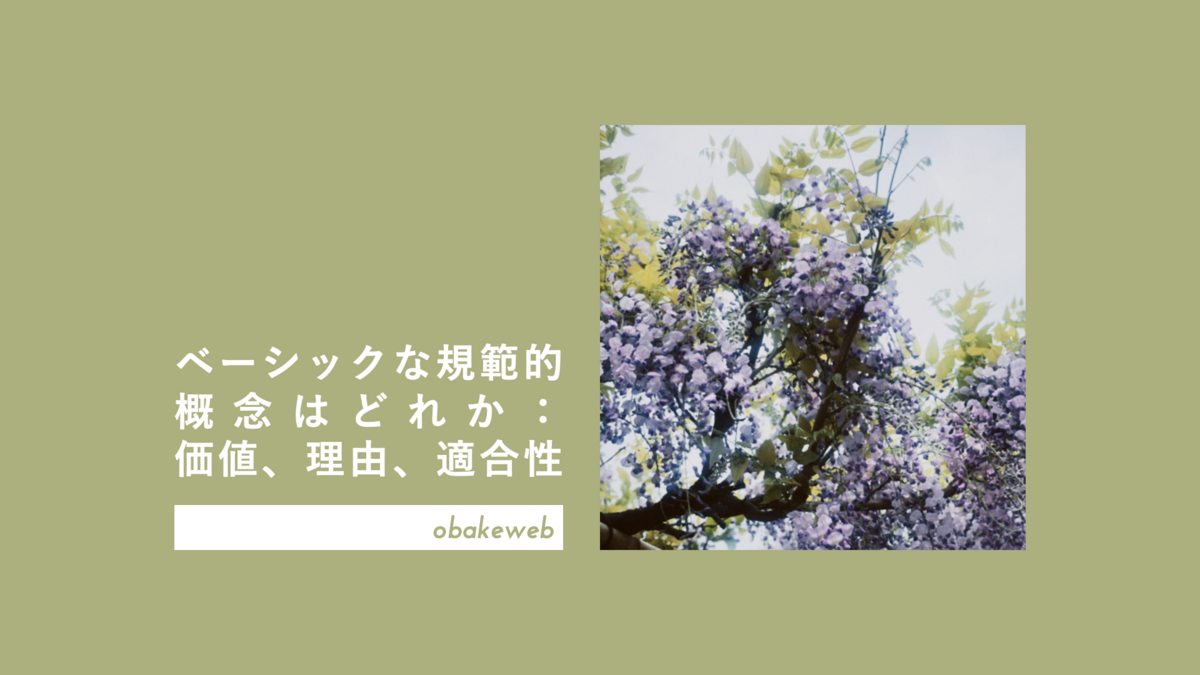
メタ倫理学というのは、どう生きればよいのかをめぐる規範倫理学に対し、そこに出てくる「良い[good]」や「べき[ought]」はそもそもなんなのかを考える分野である。私の専門は美学だが、美学は広義の価値論の一種であり、とくに最近はメタ倫理学方面の知見を引っ張ってくる美学者も多い。なので、私もコツコツ勉強しているが、まだ役牌ポンで上がれるようになったぐらいの段階だ。
私は美的価値をやっているので、自ずと関心は価値[value]ないし良さ[goodness]に関するメタ倫理学に集中している。最近、以下を読んである程度議論のポイントが分かってきたので、メモを兼ねて紹介しておく。
- McHugh, Conor, and Jonathan Way. 2016. “Fittingness First.” Ethics 126 (3): 575–606.
- Rowland, Richard. 2017. “Reasons or Fittingness First?” Ethics 128 (1): 212–29.
- Keller, Roberto. 2022. “Goodness beyond Reason.” Thought: A Journal of Philosophy 11 (2): 78–85.
- Value Theory (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
- Fitting Attitude Theories of Value (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
問題はこうだ。世界には価値を持ったものがあり、私たちにはあれする理由があったり、これするべきであったり、それをするのが適切だったりする。ここには、「価値[value]」「理由[reason]」「べき[ought]」「適切[fit]」が現れているが、これらが互いに独立していると考えるのは難しい。よりベーシックなものがあり、それを使って他の規範的概念を還元的に説明できるのではないか、というわけだ。例えば、
- べきを理由で説明する:Vするべきであるとは、Vする十分な理由があるということに過ぎない。例えば、友達のお見舞いに行くべきであるとは、そうする十分な理由があるということ。
- 価値をフィットで説明する:価値があるとは、pro態度(称賛など)をとることが適切であるということに過ぎない。例えば、ある人が善人であるとは、その人を称賛することが適切であるということ。
どの規範的概念を中心としてメタ倫理学をやっていくのか、というのが対立ポイントである。歴史的には、現代メタ倫理学の出発点となった『倫理学原理』(1903)で、G・E・ムーアが価値を中心にやっていこうとしたのだが、ムーアの言う還元不可能なgoodnessがあまりにミステリアスで訳わかんなかったので、後にべき派/理由派/フィット派が台頭した、という流れっぽい。もちろん、価値/べき/理由/フィット以外の候補があってもよいのだが、おおむねこの四つが有力みたいだ。
べき派のことはよく分からないので脇に置くが、今日の論壇ではとりわけ理由派とフィット派がバチバチにやり合っているようだ。
1 理由派:バックパッシング説
理由派の代表はT・M・スキャンロンとデレク・パーフィットで、とくにスキャンロンの『What We Owe to Each Other』(1998)がバイブル的扱いになっている。スキャンロンは、彼のアプローチをバックパッシング説(責任転嫁説)と呼んでいるので、理由派のことをこれで呼ぶ場合も多い。
価値のバックパッシング説によれば、あるものが良いとは、pro態度を取る理由があるということだ。これを使えば、例えば美しい絵画とは、感動したり、欲したり、人に勧める理由があるということになる。*1
理由ファーストのアプローチは、それ以上なんとも言えないものとして「価値」がどっしり鎮座しているというムーア的な世界観よりも、直観的にしっくりくるポイントが多い。良いものや悪いものをめぐって、私たちがあれこれ反応する理由を持つというのは、生活の実感に即しているだろう。
価値を理由で説明する試みには、しかし、有名な反例がある。そうしなければ世界を滅ぼすぞと悪魔に脅されていれば、私たちにはその悪魔を称賛する理由がある(なんといっても、世界が滅ぼされては困るのだ!)。しかし、どう考えても、その悪魔は良いヤツではない。つまり、理由はあっても価値がないケースがあるのだ。これを、誤った類の理由問題[wrong kind of reasons problem]と呼ぶ。理由に対応づけると、ありそうにないところにもあちこち価値があることになるので、これを価値多すぎ問題と言ったりもする。
悪魔を想定するまでもなく、同様の問題は日常的に生じる。若者の話題についていきたいのなら、私には積極的に猫ミームを見たり称賛する理由、つまりpro態度をとる理由がある。しかし、そんな理由があるからといって、猫ミームが良いものなわけではない。私は、自分の置かれた立場や状況次第であれこれする理由を持つが、これら理由の存在はアイテムの価値と関係なさそう、というのが問題となる。
このことは、価値と理由が双条件的関係にないのでは、という懐疑として言い換えられる。つまり、(1)価値があるなら必ずpro態度をとる理由があるにせよ、(2)pro態度をとる理由があれば必ず価値があるとは言えそうにないのだ。「価値⇒理由」だが「理由⇒価値」ではないので、「価値⇔理由」にならない、というわけだ。どうやらスキャンロンですらこの辺あまり自信がないらしい。
McHugh and Way (2016)は理由ファースト説を次のように評価している。理由ファースト説は、(1)価値のミステリアスさを取り除いてくれる、(2)端的なgoodだけでなく、good forや限定的良さ[attributive goodness]も統一的に説明してくれそう、(3)理由と価値の直観的な結びつきを捉えている、といった利点があるが、(4)誤った類の理由問題という深刻な問題を抱えている。
2 フィット派:適合態度理論
したがって、マクヒュー&ウェイがより有望だとみなすのは、フィット派である。こちらはこちらで、フランツ・ブレンターノやA・C・ユーイングを先駆者とした、それなりに歴史のある立場だ。フィット派はふつう、適合態度理論[fitting attitude theory]と呼ばれている。
こちらは前に美的価値についての適合態度分析を紹介したことがあるので、概要だけかいつまんで復習しておこう。フィット派は、価値があることを、pro態度にフィットしている、適している、値している、あるいはpro態度を取ることがふさわしい、適切、正しいことから分析する。日本語だとわかりにくいが、英語の価値用語には「-able」という形容詞がけっこうある。フィット派によれば、admirable(立派な)な人とはadmireするに値した人であり、desirable(望ましい)なアイテムとはdesireするのが適切なアイテムである。同様に、goodとは要はvaluableということであり、価値づける[value]=pro態度をとるのに値しているということだ。こうして、価値をフィットから説明するのが適合態度理論である。
フィット派は、少なくとも彼らが考えるところでは、誤った類の理由問題を回避している。そうしなければ世界を滅ぼすぞと悪魔に脅されていれば、私たちにはその悪魔を称賛する理由があるが、だからといって、悪魔が称賛に値しているわけではない。そんな悪魔はむしろ非難に値するのであり、称賛は不適切である。脅されている以上、「こんなヤツを称賛する理由なんてない!」というのはおかしい(脅しがまさに理由なのだから)。しかし、脅されているからといって、「いやぁ、悪魔さまを称賛するのは適切ですなぁ」というのもおかしい(脅してくるようなヤツなので)。
よって、価値を説明する上で、フィット派は理由派より有望だ、というわけだ。マクヒュー&ウェイによれば、適合態度理論は、バックパッシング説の魅力(1)(2)(3)を引き継ぎつつ、これを悩ませていた(4)誤った類の理由問題を回避できる。
3 誤った類の理由問題にどう対処するか?
もちろん、理由派も黙っちゃいない。擁護者たちは、誤った類の理由問題にどうにか対処する方法を日々編み出そうとしている。理由派の戦略はおおきく、(1)悪魔を称賛する理由がある、というのをどうにか否定する、(2)理由はあるが、それは誤った類の理由に過ぎないので放っておいてOKとする、に分かれる。前者はその理屈を提示しなければならないし、後者は誤った/正しい類の理由という区別をちゃんとしなければならない。
後者の試みとして人気なのが、対象由来[object-given]な理由と状況由来[state-given]な理由を区別して、正しい/誤った理由に対応づけるというものだ。悪魔に脅されているケースでは、悪魔という対象のあり方(性格など)に由来して称賛の理由が生じるのではなく、脅されているという状況に由来して理由が生じる。同様に、猫ミームのあり方(ユーモラスでかわいらしいなど)ではなく、若者ウケという状況に由来した理由である限りで、これは誤った類の理由である。この区別を使えば、「価値⇔正しい類の理由(=対象由来の理由)」という双条件文を維持できる、というわけだ。
【2025/03/02 state-givenの理解が間違っていたので、以下のように修正しました。】
後者の試みとして人気なのが、対象由来[object-given]の理由と態度由来[state-given]の理由を区別して、正しい/誤った理由に対応づけるというものだ。悪魔に脅されているケースでは、悪魔という対象のあり方(そいつの性格など)に由来して称賛の理由が生じるのではなく、称賛という態度のあり方(それによって世界滅亡を回避できる)に由来して理由が生じる。同様に、猫ミームのあり方(ユーモラスでかわいらしいなど)ではなく、しかじかの態度を取れば若者ウケに繋がることが理由の中身なので、誤った類の理由に相当する。この区別を使えば、「価値⇔正しい類の理由(=対象由来の理由)」という双条件文を維持できる、というわけだ。
対象由来/態度由来の理由という区別が、十分に一般的なものであるのかは、それなりに疑われている。実際、マクヒュー&ウェイはこれも含めて、どんな区別も正しい/誤った類の理由の区別としてうまくいってないと評価している。
応答としてRowland (2017)は、行為の付随的帰結[additional consequence]を理由として行為するときの理由は誤った類の理由であると主張している。世界滅亡を防げるというのは、悪魔を称賛した場合の付随的帰結であり、したがって、これは悪魔を称賛する誤った類の理由に過ぎない。価値を分析するなら、そうでない正しい類の理由を使えばOKというわけだ。
逆襲としてローランドは、誤った類の理由問題は適合態度理論にとっても無縁ではないとしている。マクヒュー&ウェイによれば、なんにせよ、理由派は反例を回避するためにさらなる条件を立て、なぜこの条件が成立するかについては「理由とはそういうものだから!」と言い張るしかないが、ローランドによればフィット派だってそうだ*2。つまり、誤った類の適合性という似たような問題があり、これに対処したければフィット派はどこかでは「適合性とはそういうものだから!」と言い張るほかない条件を立てる必要がある。
そもそも「適合性[fittingness]」なんて概念をベーシックとするのは、価値というミステリアスなものをベーシックとしたムーアとたいして変わらんだろう、という批判もよくなされている。それを言ったら「理由[reason]」だって……というどっちもどっち合戦が続いているようだ。
4 価値派
ところで、価値派もすっかり見放されたわけではない。よく知られているように、規範倫理学はおおむねベンサム的な功利主義、カント的な義務論、アリストテレス的な徳倫理学に分かれて派閥争いをしているが、このうち最後の陣営が、価値vs理由vsフィットという争いにおいては価値派を強く動機づけている*3。いわゆる新アリストテレス主義者と言われる面々、フィリッパ・フット、ロザリンド・ハーストハウス、ジュディス・ジャーヴィス・トムソンらに触発されつつ、価値派はムーア的な見解を蘇らせようとしている。
価値派のKeller (2022)は次のような例を挙げている。水は人にとって良いものである。理由派なら、要は水は人にとって欲する理由がある、と言いたがるだろう。しかし、水は植物にとっても良いものである。だが、水は植物にとって欲する理由があるというのは変だ。植物は欲したりしないし、理由を踏まえて行動することもない。理由ファースト理論は、このような自然物にとっての良し悪し、自然的規範性を説明できないのだ。
理由派は、いや、そもそも行為者性のない自然物には規範性なんてないんじゃ!と応答したり、Good forの分析は諦めて端的な良さの分析に撤退するかもしれない。ケラー流(というか価値派流)の反例はフィット派にも当てはまるかもしれない。
ということで、今日もみんなして理由なしの価値やフィット、価値なしの理由やフィット、フィットなしの価値や理由のケースをぶつけ合って、ああでもないこうでもないとやり合っている。
5 雑感
規範的概念としてベーシックなのはどれか。
私の意見はまだまだ固まっていないが、もともと強く帰結主義的な直観を持っていたのもあり、価値派に傾いている。トムソンの『Normativity』に触発されたのもあって、最近は帰結主義から徳理論に傾きつつあるが、どちらにせよ価値ファースト理論だ。まだまだ感化されやすい段階にあるので、おすすめの論文や本など教えてください。
*1:理由派、とくにスキャンロンまわりの議論は、最近日本語でも読めるものが多い。例えば以下を参照。
- 岡本慎平「T.M.スキャンロンと価値の責任転嫁説明:「理由への転回」の里程標」2018
- 安倍里美「価値と理由の関係は双条件的なのか:価値のバックパッシング説明論の擁護」2019
- 高田敦史「スキャンロンの価値の反目的論」2022
*2:理由派が言い張るのは、反応条件[response condition]という有名な条件だ。これによれば、ある事実pは、pに基づいて行為Vできるようなものであるときに限り、Vする理由である。知らんけどたぶん、「べきはできるを含意する[ought implies can]」とか、理由の内在主義(動機づけ理由になれるものだけが規範的理由である)に繋がる話だ。(今更だが、本エントリーが理由理由言ってるのは、一貫して規範的理由のことだ。)