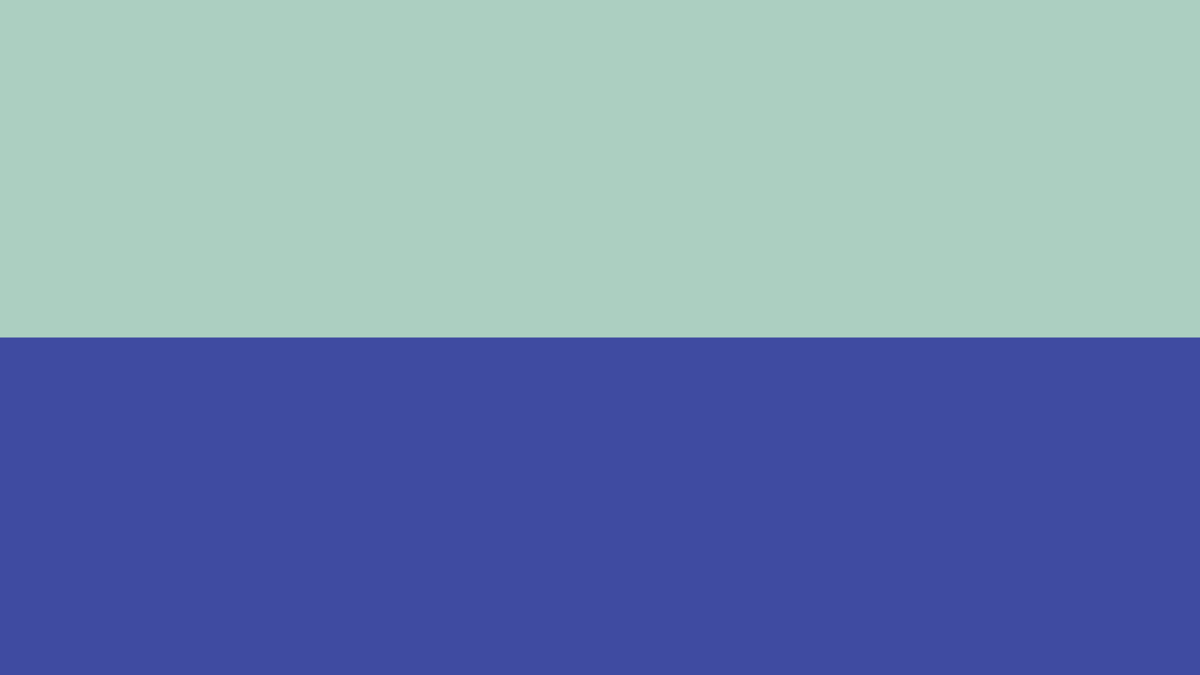
モンロー・ビアズリーの「美的観点」という論文を翻訳しました。最新号のフィルカル6(2)に載っています。論文の中身や背景については訳者解説も付けているので、そちらをどうぞ。
20世紀分析美学の礎を築いた巨人を三人挙げるとすれば、ビアズリー、シブリーはほぼ確定として、個人的に3人目はディッキーだと思っているが、ウォルハイムでしょ(美術批評の人じゃん)、いやいやグッドマンだ(なにをいう奴は言語哲学者だ)、ダントーに決まっている(ヘーゲリアンはNG)などと揉めるところか。ともかく、ビアズリーの功績は満場一致で認める(べき)ところだろう。
「美的観点」は1970年に出版された論文。主著の『美学』が1958年出版なので、ひとしきり批判や応答が終わったあとで、自説を整理するような内容になっている。ビアズリーの理論を概観するのに便利なテキストであり、1982年の同名論集『美的観点』でも筆頭論文として収録されている。
読んでいただければ分かるように、ビアズリーの立場は結構トガッたものである。賛同するにせよ批判するにせよ、こういう立場が分析美学の歴史において重要な位置を占めてきたことは知っておきたい。
ともすれば「分析美学」は、ある種のやり方において芸術や美的経験を考える手法として理解されており、("ある種のやり方"が曲解されていない限り)それはそれでよいことなのだが、学統としての分析美学を知るためにその歴史をあたるのもよいことだろう。とくに、日本語でアクセスできる情報はまだ多くないので、その助けになったとしたら幸いだ。
訳は「分析美学第一世代をちゃんと読む会」にて検討いただいた。とりわけ、高田敦史さん、森功次さんには通しでコメントをつけていただいた。また、一度校了となった後で重大なものを含む誤植がぽんぽんと見つかり、フィルカル制作部さまにはたいへんなご迷惑をおかけした。皆さまのおかげで多くの醜態を回避できました。ありがとうございます。
余談(A)アントニオーニの『欲望』
論文の終盤でビアズリーはミケランジェロ・アントニオーニの『欲望』(1966)に触れている。ほかの観点をないがしろにしてまで美的観点ばかりとってしまうことの弊害を語っている箇所であり、『欲望』もまたこれを主題とした映画だと語っている。
ビアズリーは「泥沼にはまるのは嫌なので、こう述べるのはかなり気が引ける」と自信なさげだが、実際、私はこのような仕方で『欲望』を要約してしまうのはいくらか的外れだと思っている。
たしかに、主人公の若手写真家は仕事に貪欲で、モデルに対して横柄であり、通行人でも平気で盗撮するという意味では、モラルの欠けたヤバいやつだ。そういう意味では、道徳的観点よりも美的観点を優先する人物のように思われるかもしれない。しかし、この話には一捻りある。主人公の本業はコマーシャル写真なのだが、モデルを撮影する仕事にはうんざりしており、自分としてはもっと生々しい現実を切り取った報道写真がやりたいと思っている(し、ウォーカー・エバンス風の写真を編集者?に売り込む場面もある)。やがて、偶然撮影してしまったなにかに取り憑かれて、真相究明へと奔放するのも、こういったジャーナリスティックな意欲があってのことだ。
すなわち、『欲望』の中心となるパラノイアは、認識論的なパラノイアではあるが、ビアズリーが述べたような美的なパラノイアではない。もちろん、芸術写真という分野において認識論的なものと美的なものは容易には切り離せない、という事情はあるだろう。それでも、ビアズリーが厳密に定義したところの「美的観点」(事物の形式的統一性や領域的質の強度にフォーカスするもの)が前景に来るような話とは思われない。
あるいは、なんの脈略もなく巨大なプロペラを購入するくだりを踏まえて、ビアズリーは「あんなガラクタまで美的観点で見ちゃう写真家」だと考えたのかもしれない。その解釈もいまいちな気がするが、プロペラに関してはなんにも分からない。作品を見てもらえれば分かるが、プロペラは物語の筋にはまったくと言っていいほど絡んでこない。端的に言って意味不明なのだ。
『欲望』はかなりいい映画だと思うのだが、ビアズリー的な意味での統一性(一貫性、完全性)に反する要素がかなりある。残念ながら、ビアズリーが『欲望』を気に入ったのか気に食わなかったのかは分からない。
余談(B)「翻訳と裏切り」
アーサー・C・ダントーに、「翻訳と裏切り」という題の短いコラムがある。イタリア語には「Traduttore traditore」という格言があり、おおむね「翻訳家は裏切り者だ[The translator is a betrayer]」という意味になるが、こうやって翻訳すること自体が裏切りへの加担となってしまう。イタリア語では「Traduttore」と「traditore」がいわばダジャレになっているのだが、「翻訳家は裏切り者だ」や「The translator is a betrayer」ではそのことが分からない。このように、翻訳家の裏切りとは第一に、原文を忠実に移し替えることができず、原文の重要なニュアンスやイメージやリズムを失ってしまうことを指す。完全に正確な翻訳などありえない、というわけだ。
一方で、ダントーはもうひとつの裏切りについて語る。それは、「知識は力である」という事実と関わるものだ。ある人ないし集団だけが知っている秘密は、まさに秘密であるがゆえに彼らが独占している力(権力といってもよい)である。これを他者ないし他集団に共有することは、彼らの独占していた力を失わせることになる。
秘密の言葉は、それが秘密である限りで力を与えてくれる。それを翻訳し、その知識と力を外国人[alien]の手に受け渡すとき、私は秘密を裏切ることになる。(Danto 1997: 62)
それはちょうど火を盗んで人類に与えたプロメテウスのような裏切りである。このような裏切りは、翻訳の不可能性よりもむしろ、翻訳できてしまうことを前提としている点で、第一の裏切りとは性格を異にする。翻訳には、民主的で、反権力的な性格がある。
今日の世界において、学術的な書き物はそれを読むのに解釈学的な努力を要するほど不明確な様相を呈している。あたかも解釈学者を念頭において書かれているかのようだ。それは権力と権威の基盤にほかならないため、明晰な散文に翻訳しようなどというのは裏切りであり、権力と権威を消滅させてしまう、というわけだ。解釈者は、彼らなりのやり方でテキストを独占する聖職者カルトなのだ。翻訳が裏切りなどというのは、彼らに勝手にそう思わせておけ!(Danto 1997: 63)
力強い文章だ。この最後の段落に至って、話は不明確さと明確さをめぐる議論にまで踏み込んでいる。もちろん、複雑なことを複雑なまま理解することは知の本分であり、明確化には単純化の危うさがあるので、一概にはなんともいえない話題だ。それでも、第一の裏切りに苦悶し、第二の裏切りを引き受ける(プロメテウスになる)ことはやはりひとつの美徳なのだろう。
翻訳は中学のころから携わりたかった営みのひとつであり、実際に携わっていて精神衛生上かなりよい営みだと分かった。今後も続けていきたいので、うまい話があったらこっそり教えてください。