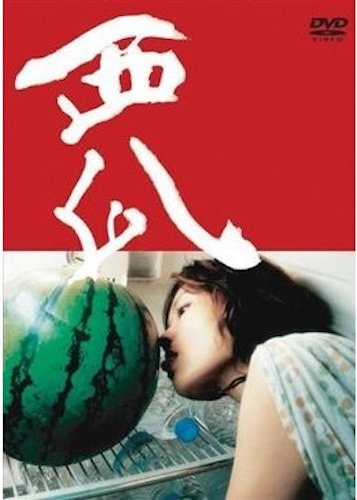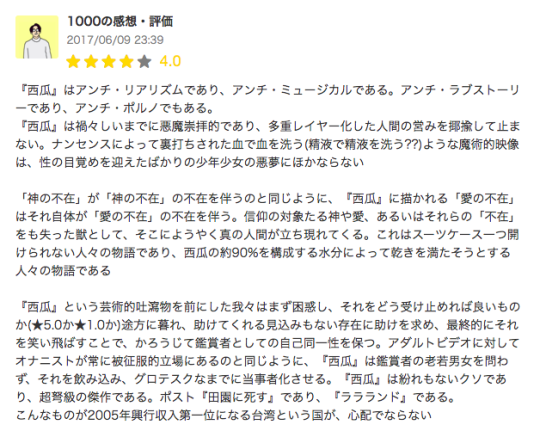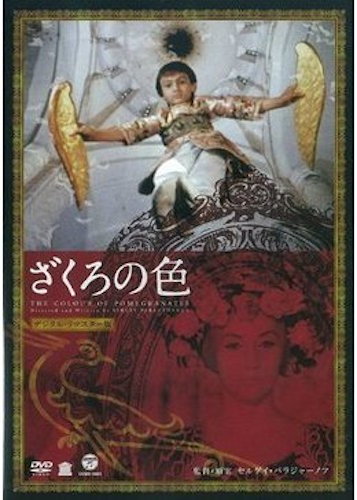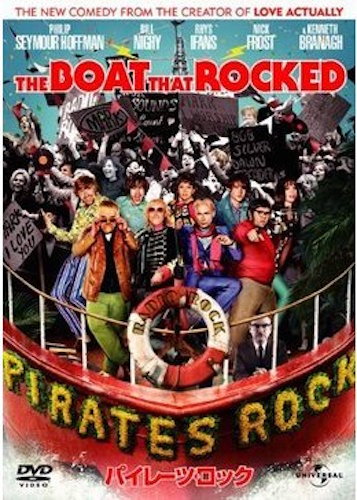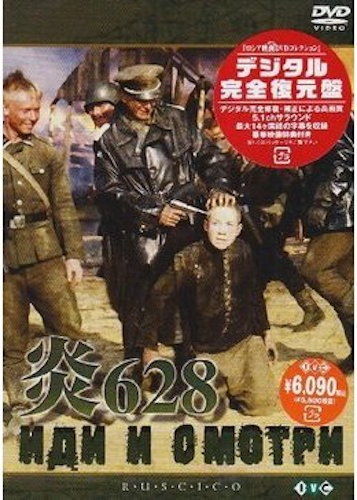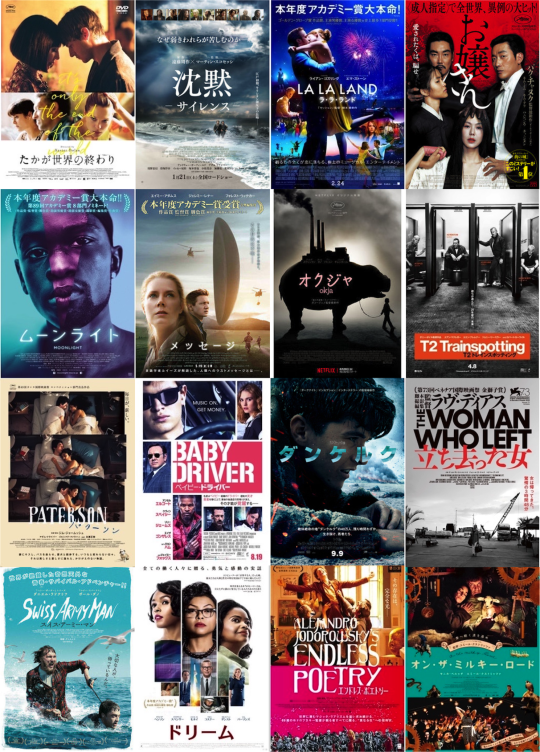『分析美学基本論文集』からつまみ読み。ケンダル・ウォルトンによる1978年の論考「フィクションを怖がる(Fearing Fictions)」に関するメモと雑感です。
ホラー映画に対して「怖かった」と言うけれども、それって本当に「恐怖」だと言えるのか?って話。
①恐怖とは身に危険が迫ることへの信念から生じる。➡現実に危険への信念がなければ「恐怖」とは「言えない」。
②ホラー映画の鑑賞者は、自分が現実には安全だとしっかり「理解している」。➡現実に危険があるとは「信じていない」。
よって①と②は矛盾しているので、ホラー映画に対して「怖かった」と言うのは誤りである。しかし……
実際彼は、現実世界のまさにいま起ころうとしている大惨事を恐れる人の状態と、いくつかの点でまぎれもなく同じ状態にある。彼の筋肉は緊張し、ぎゅっと椅子をつかむ。鼓動が早まり、アドレナリンが湧き出る。(p.303)
身体的には実際に「怖がっている」のだと。ウォルトンはこれを暫定的に「準恐怖」と定義する。これをもとにウォルトンは、鑑賞者が現実的なレベルではなく、ヴァーチャルなレベルで”怖がっている”ことを説明していく。
手始めに「いやいや、”現実に”怖がっているでしょ」という反論への再反論を行う。
①危険はないと完全に理解している、というけど、実は半信半疑なんじゃね? 半分は現実に危険だと信じているんじゃない?
➡多少なりとも信じているなら、逃げ出すとか警察を呼ぶとか、多少はそういった行動をしようと思うはず。実際にはそんなことする人いないので、「半分は危険性を感じている」ってのは間違い。
➡あるいは――震え上がるような身体的な反応は、どう考えても「半分だけ危険性を感じている」人の振舞いではない。どちらかと言うと「100%怖がっている」人のそれに近い。よって、別の説明が必要である。
②知的には「危険性がない」と分かっていても、「直感的」には危険を感じているのでは?
➡「怖いから観るのを辞める」といった、本来行うはずの「意図的行動」とらない。自動的な反応(動悸、汗)だけが起きる。つまり直感的にも危険性は「感じていない」。
③意図的行動をとらないと言うけど、それって恐怖が「瞬間的」すぎて反応できないだけでは? 少なくとも瞬間的には危険を感じているんじゃね?
➡ホラー映画を観ている間の反応は持続的。怖がっているというのなら、映画の間ずっと"怖がっている"。
➡恐怖ほかにも、憐れみや称賛など、鑑賞中以外にも感情は持続する。よって、それは「瞬間的」ではない。
最終的に「怖がっている」「怖がっていない」を両立させたいウォルトンは、ここから「虚構的真理」という概念を導入する。というのも「水は100℃で沸騰する」というのは観測可能な真の命題だが、フィクションだとややこしい話になる。
「桃太郎は鬼を退治した」というけれど、”現実には”桃太郎も鬼も存在しないので、当然”退治する”こともできない。かと言って、「桃太郎は鬼を退治した」というのが偽かと言うと、それも違和感がある。
要するにこの命題は、「『桃太郎』という昔話(=虚構世界)において、桃太郎は鬼を退治した」と言い換えれば、真の命題になるのだ。これが虚構的真理。
虚構的真理は単に「想像」することによって作られることもあるが、より重要なのはルール付けされた原則によってもたらされるケースだ。例えば、鬼ごっこで鬼をやる子供は、現実には醜悪で凶暴な怪物の「鬼」ではないが、ゲームの参加者は彼を"鬼"だとみなす「原則」のもとで、彼=鬼から逃げる。ここからウォルトンの有名な「ごっこ遊び理論 (Make-Believe Theory)」が始まる。
結論から言うと、ホラー映画鑑賞者は、
・現実には危険性を感じておらず、怖がっていない。
しかし
・「ごっこ上における」危険性を”信じていて”、「ごっこ上では」怖がっていると言える。
ごっこ上でそのスライムが自分を脅かしていると理解することからもたらされる一つの結果として、チャールズは準恐怖に陥っており、その事実が、ごっこ上で彼はそのスライムを恐れているという真理を発生させているのである。(p.313)
とのことだ。つまり、ホラー映画を観て「怖がる」→「飛び上がる」という一連のプロセスは、鬼ごっこの鬼を「怖がる」→「逃げる」プロセスと同じであり、特定の原則に基づいたヴァーチャルな「恐怖」なのだと言う。
あとの章は補足的な説明。我々は虚構世界の単なる「外的な観測者」ではなく、自ら虚構のレベルまで降りていくんだよー、とか。
最後に、上記で得られた理論が、どのように有用なのか説明する。
①フィクションはなぜ、どのように重要だと言えるのか?
➡古来フィクションの役割とは、「情動を浄化」してくれるものされてきた(アリストテレスとか)。つまり感情のコントロールを学ぶことだと。だとすれば、その練習は虚構世界・ごっこ遊びを通したシュミレーションによってのみ可能となる。
さらに、次のことも説明できる。
②悲劇的なバッドエンドが好きな人が、それでもなお登場人物に共感・同情しながら鑑賞するのは矛盾してない?
➡共感・同情は「ごっこ上」でのヴァーチャルなもの。悲劇を望むのは現実における嗜好。両者は両立しうる。
③オチが分かっていても熱中しながら鑑賞できるのはなぜ?
➡ストーリーに熱中するのは「ごっこ上」でのヴァーチャルなもの。現実にはオチを知っていても、それに(ごっこ上で)熱中することは可能。
などなど、非常に便利な理論だそうだ。
休憩タイム。
個人的に気になった点をいくつか。
なにより、準恐怖の位置付けがよく分からなかった。はじめのほうでは「ごっこ遊び」の結果生じるものだと思っていたが、どうやら「ごっこ遊び」そのものの媒介にもなっているみたい。準恐怖、即ち身体的な反応がどうやって生じるのかは、明らかに重要なポイントであるにもかかわらず、説明が甘い。
彼が怖がっていることをごっこ的にしている要因の一部は、チャールズが準恐怖の状態にあるという事実、つまり彼が自分の動悸の早まりや筋肉の緊張などを感じているという事実である。(p.312)
だからこそ「怖かった」という言明は可能となる。それは分かるが、上でも引用したが通り、
ごっこ上でそのスライムが自分を脅かしていると理解することからもたらされる一つの結果として、チャールズは準恐怖に陥っており、その事実が、ごっこ上で彼はそのスライムを恐れているという真理を発生させているのである。(p.313)
準恐怖の前提には「危険性アリ」という"信念"がある。これが準恐怖を生み、準恐怖(身体的な反応)が「怖かった」というごっこ遊びに基づく言明を可能にする。
じゃあ、信念ってなんだ?
最初に戻って、「現実の危険性に対する信念はない→よって現実的には”怖がっていない”」を確認すると、これって「ごっこ上の危険性に対する信念ならある→よってごっこ上では”怖がっている”」ってだけじゃね? 要するに表面的な理解を一つ下のメタに移して、なぁなぁにしているだけなのでは……。現実の”恐怖”がごっこ上の「恐怖」によって説明されるとしても、結局入れ子構造が無限に続いてしまうのではないか。
とはいえ、現実の表面的な”恐怖”が、実はヴァーチャルなレベルでの恐怖の投影なのだという指摘は興味深い。ウォルトンはこれをフィクション鑑賞のみに適応しているが、喜怒哀楽の言語ゲームを生きる我々にとって、人生も一つの「ごっこ遊び」でしかない気がする。
加えて、名前で損していると思う。「ごっこ」だとか「ふり」だとか、言葉のシニカルさだけで反論を集めているという話も聞いた。
ポストモダン的な「クールさ」を推し進めるのであれば、あらゆることはヴァーチャルになる。仕事というのは人間関係とルーチンワークの「仕事ごっこ」であり、恋愛は記念日とプレゼントの「恋愛ごっこ」でしかない。ウォルトンは、一度観たことのある作品でも「ごっこ遊び」によって感動を救い出せると言うが、それは「ごっこ上での」感動に過ぎない。現実には影しかない。
自分をどうにか騙して虚構を現実として思わせるというよりは、われわれ自信が虚構的になるのである。(p.325)
これはちょっとした名言に違いない。『マトリックス』に描かれる水槽の脳や、『インセプション』の入り組んだ夢の中で生きる人たち。ウォルトンは、そういったヴァーチャルな現実に対して「別にそれでもよくね?」と肯定しているように思えた。昔だったら僕も両手上げて同意していたが、いまではどうだろうか。なかなか態度を決められない。いずれにせよ、「クールさ」については近い内に何か書かなきゃ、と思っている。
2018/04/05補足
― ― ― ― ― ― ― ― ✂ ― ― ― ― ― ― ― ―
田村均「虚構世界における感情と行為 : ケンダル・ウォルトンの虚構と感情の理論」
― ― ― ― ― ― ― ― ✂ ― ― ― ― ― ― ― ―
この辺読んだ。疑問点があるていど整理されたので、ざっくり補足。
フィクションと情動のパラドックスについては、Seahwa Kimが以下のようにまとめている。
(1)私達は、自分の感情の対象が実在すると信じているときにのみ感情を持つ。
(2)私たちは、虚構作品の登場人物や状況が実在しないことが分かっている。
(3)私たちは、虚構作品の登場人物や状況に対して感情を持つ。
(田村 pp.3-4)(*引用者強調)
このうちどれかを否定しないと、矛盾が発生するという寸法。ウォルトンは(3)を否定して、「現実の感情ではなく、ごっこ上の感情やで」というわけ。
フィクション作品”として”鑑賞する際には(2)はおおむね自明だとして、個人的には(1)を否定したほうが手っ取り早くないか?と思ったが、いわゆる「感情の認知主義」というヤツはなかなか強固らしい。
つまり、①真実であり、真実だと知っている、②嘘だが、真実だと信じ込んでいる、③真実だが、嘘だと思いこんでいる、④嘘であり、嘘だと知っている、のうち①②に対してのみ感情装置は起動する。しかし(2)は要するに④であり、こうして(1)と(2)がぶつかる。
だからこそ「実在すると信じているときにのみ」の「のみ」って部分を外せばいいんじゃね、と思うが、結局「④嘘であり、嘘だと知っていることに感情を抱くのはなぜか」というわけで、もとの問題に戻ってくる。(1)を否定しようとすると、その中から飛び出してきた④が、再度(1)(2)(3)の矛盾をもたらすのだ。結局人間は刺激に対して条件反射をしているだけなのだ、とか、そういった解答が必要になってくる。
僕自身はジョン・サールの思考実験「中国語の部屋」で切り込めるんじゃないか、って思った。実験について詳しくはウィキペディア参照。
たとえ中国語を理解していなくても、マニュアルがあれば中国語でメッセージをアウトプットできる。情動というのも、社会的慣習や個人的嗜好がまとめられたマニュアルをもとに、自動的にアウトプットされたものではないか。だとすれば、虚構中の世界そのものが実在するかどうか、ましてや鑑賞者がその実在を信じているかどうかは問題にならない。人間機械論みたいで我ながらディストピアじみているが、「虚構上では確かに怖がっているが、現実上では怖がっていない」なんていうよりもすっきりするじゃない。
余談だが、去年の東京フィルメックス映画祭でワン・ビン監督の『ファンさん』という作品を観た。アルツハイマーのファンさんを捕らえたノンフィクション作品らしいが、前情報が一切なかった僕は最後の最後までフィクションかどうかわからないまま観終わった。ウォルトンだったらこれを「不完全なごっこ遊び」とでも呼ぶだろうか。僕は結局「もやもやした微妙な気持ち」のまま観終わったが、仮にノンフィクションだと知っていたとして、ファンさんへの同情が増しただろうか。あるいはそうかもしれない。
逆にあれがフィクションで、僕自身そのことを知りつつ観ていたとしたら、「これは作り話で、ファンさんを演じている人は本当はアルツハイマーじゃないんだ」と認識しつつ、意識下で「ファンさんが実在するというごっこ遊びのもとで、ごっこ上の同情を抱く」ことができただろうか。これはちょっと怪しくないか。(断定はできないけど)
もちろん、「フィクションかノンフィクションか」についての認識は、アウトプットされる情動に少なからず影響するだろう。しかし、「実話かどうか」は近年の創作においてますますあやふやになってきている。そもそもドキュメンタリー映画だって、カメラによって切り取られた瞬間から、それはもはや現実たりえない。これを逆手に撮って、フィクションっぽいノンフィクションにしたのが『ファンさん』だろうし、先々月ぐらいに話題になった『スリー・ビルボード』はノンフィクションっぽいフィクションを意識しているだろう。素朴な言い方だが、鑑賞者にとっては「どっちでもいい」のであり、それよりもカメラワークや音楽といった手法的な部分が大きな影響力を持っている。「フィクションだと認識しているかどうか」が、アウトプットされる情動が「真の情動」なのか「準情動」なのかを左右するというのは、直観的に見て疑わしい。だったら「中国人の部屋」説みたいに、刺激に反応するだけの人間像を思い描いたほうが、好都合なように思える。
ほかにもいろいろツッコミどころを見つけたが、これぐらいにしておこう。ひとまずは、僕レベルでも思いつくような疑問にちゃんとツッコんでくれている人がいるのを確認したということで、一安心だ。